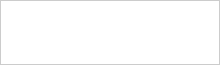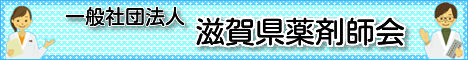滋賀県薬剤師会 薬物乱用防止アクションプラン2025
はじめに
薬物の乱用は、乱用者個人の健康を蝕むのみならず、周囲の人たちの生活をも崩壊させ、また凶悪な二次犯罪を引き起こさせるなど社会に対しても大きな危害をもたらしています。薬物乱用による事件・事故は、法律の改正等により規制が強化されていますが、依然として後を絶ちません。今般発出された 医薬総発1030第3号 医薬安発1030第1号 令和6年10月30日「過量服薬による少年の非行等の防止に向けた警察庁からの協力依頼について」はまさしく地域の薬剤師・薬局に適切な対応を強く求めている項目です。こうした近年の諸問題から、日本では二次・三次予防に対する早急な対応が迫られている一方で、一昨年厚生労働省が策定した『第六次薬物乱用防止5か年戦略』では戦略目標のひとつ目に「青少年を中心とした広報・啓発を通じた国民全体の規範意識の向上による薬物乱用未然防止」とあり、一次予防を廃止・縮小することは二次、三次予防にかかるコストの上昇、特に社会保障費の増大、就労人口の減少などが懸念されます。
薬剤師会は学校薬剤師活動の中で児童生徒に対して薬物乱用防止啓発活動を行っていますが、授業時間は小中9年間で2時間程度であり極めて短時間です。
しかしながら高校生の95%ほどが「薬物乱用は良くない事、誘われたらきっぱり断る」との調査結果を踏まえた国会答弁もあり、一定の効果を有しています。一方でコロナ禍以降、10代を中心に市販薬の過剰摂取(オーバードーズ(OD))が広がっており、深刻な社会問題となっています。OD問題は虐待やネグレクト、孤立、不安、生きづらさなどの背景となる課題に早期に介入するなどの医療福祉の手助けと連携を要することからも、OD問題が生じるより前の段階において社会全体で児童生徒を守っていくとういう明確なメッセージを発信していく必要があります。
児童生徒や地域住民に対する規範意識の維持向上に向けた広報や、ライフスキルの形成を交えた啓発など、一次予防を強化する事が効果・費用的にも重要です。以上から、下記のアクションプランをもとに滋賀県の実情を踏まえた取り組みや事業を実施することで薬物乱用を未然に防ぐとともに医薬品の適正使用を推進し、県民の福祉と健康増進に貢献します。
アクションプラン
1.効果的な一次予防の実施
・地域住民への啓発・規範意識の向上
・県民全体のヘルスリテラシー向上やライフスキル、ソーシャルスキルの形成・向上を目的とした啓発
・学校薬剤師による啓発・プレコンセプションケアを含む健康教育の実施
・薬局における各種啓発の実施2.二次予防の推進
・一般用医薬品の適正な販売体制強化
・一般用医薬品販売における警察等関連機関との連携3.会員への知識の普及・研鑽
・各研修会の実施2025年4月1日